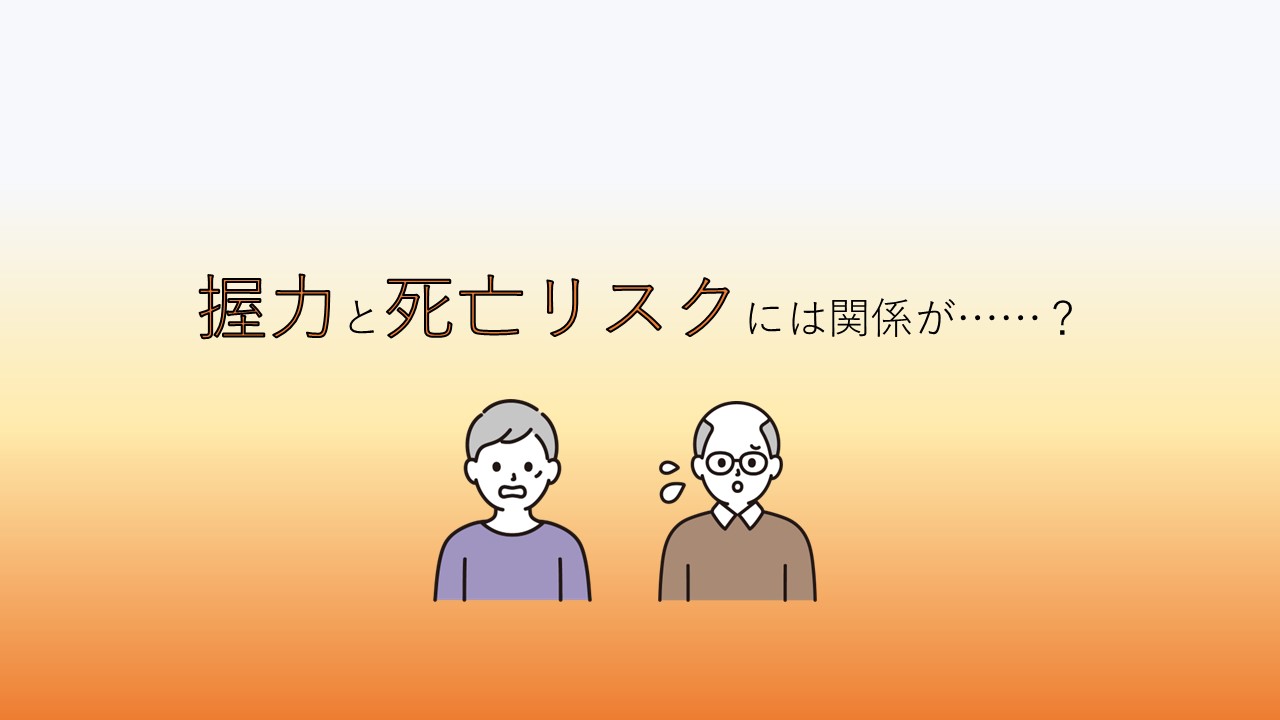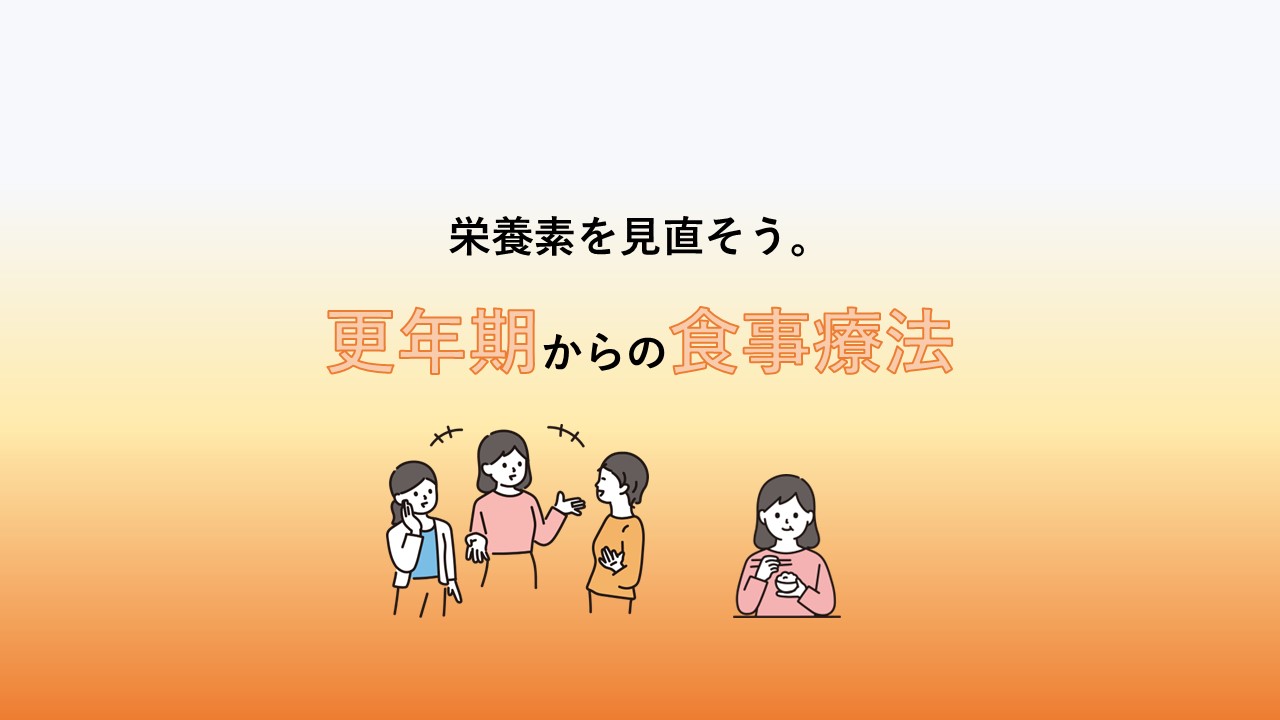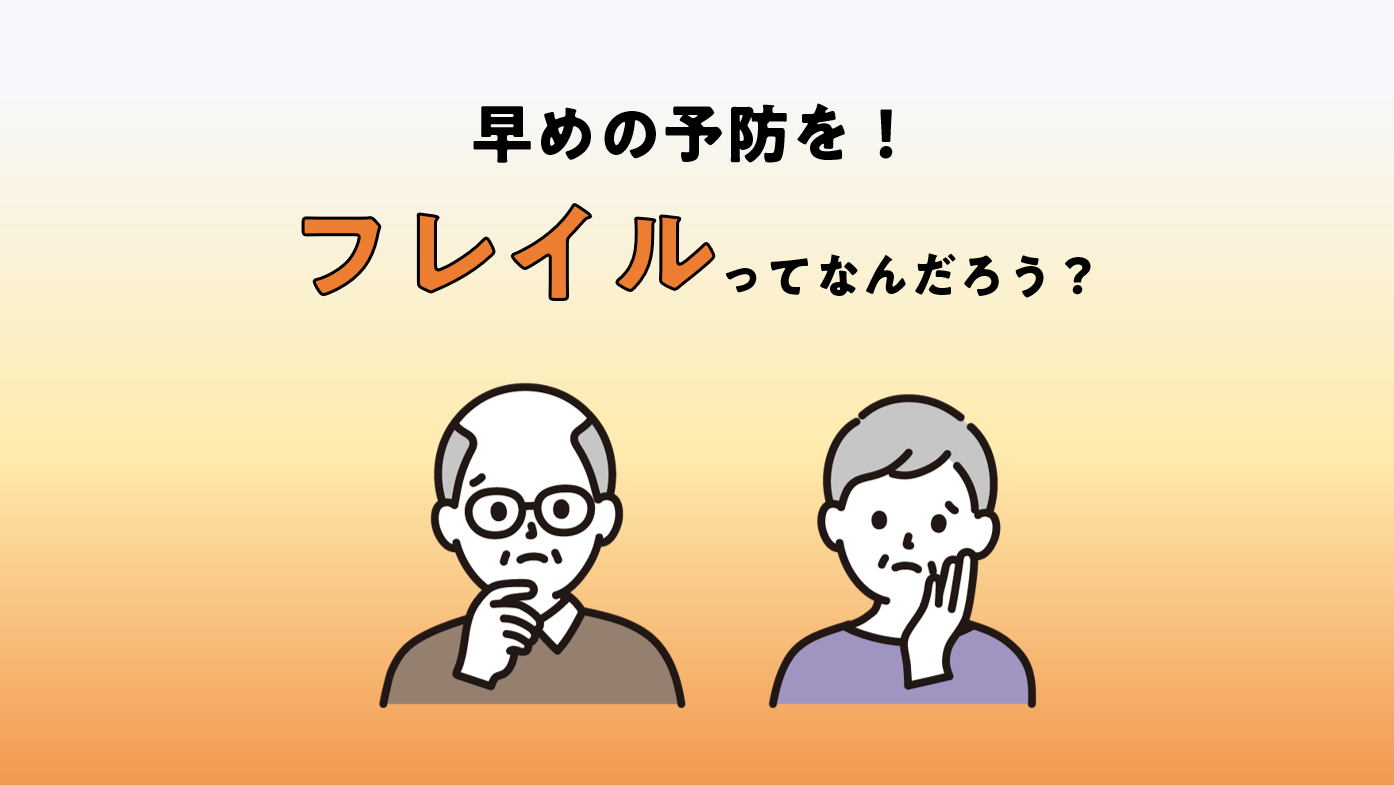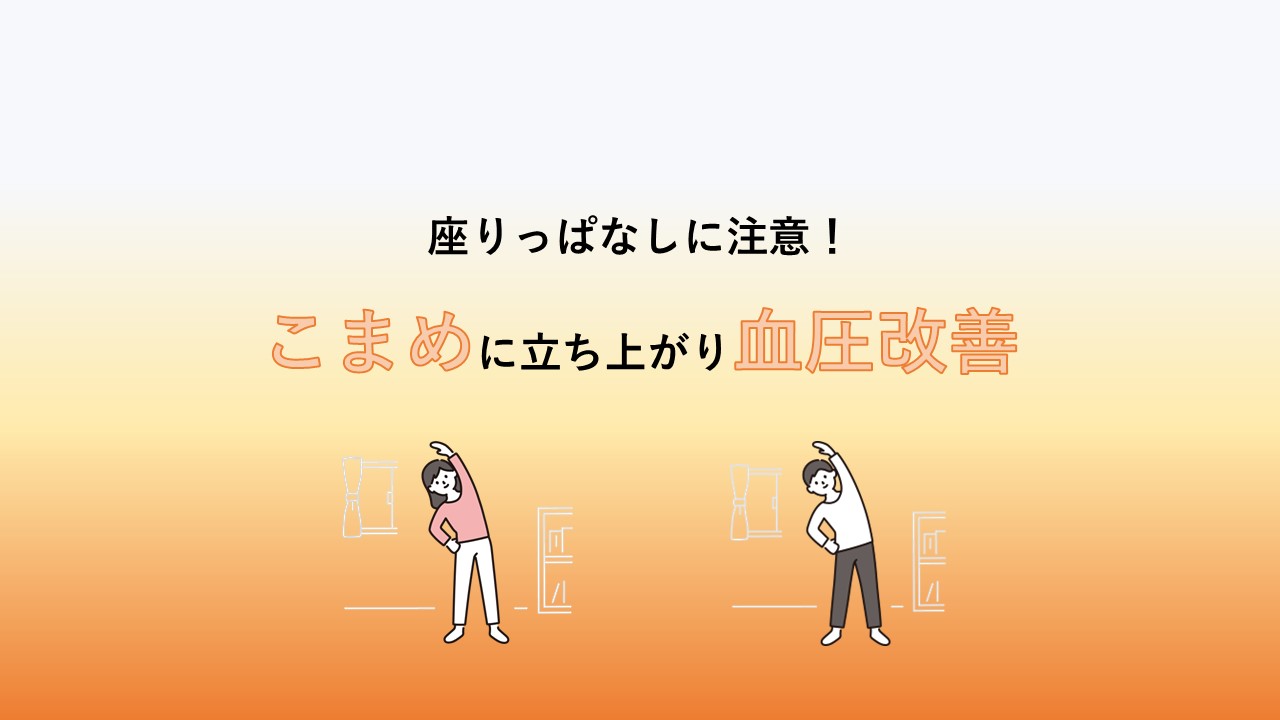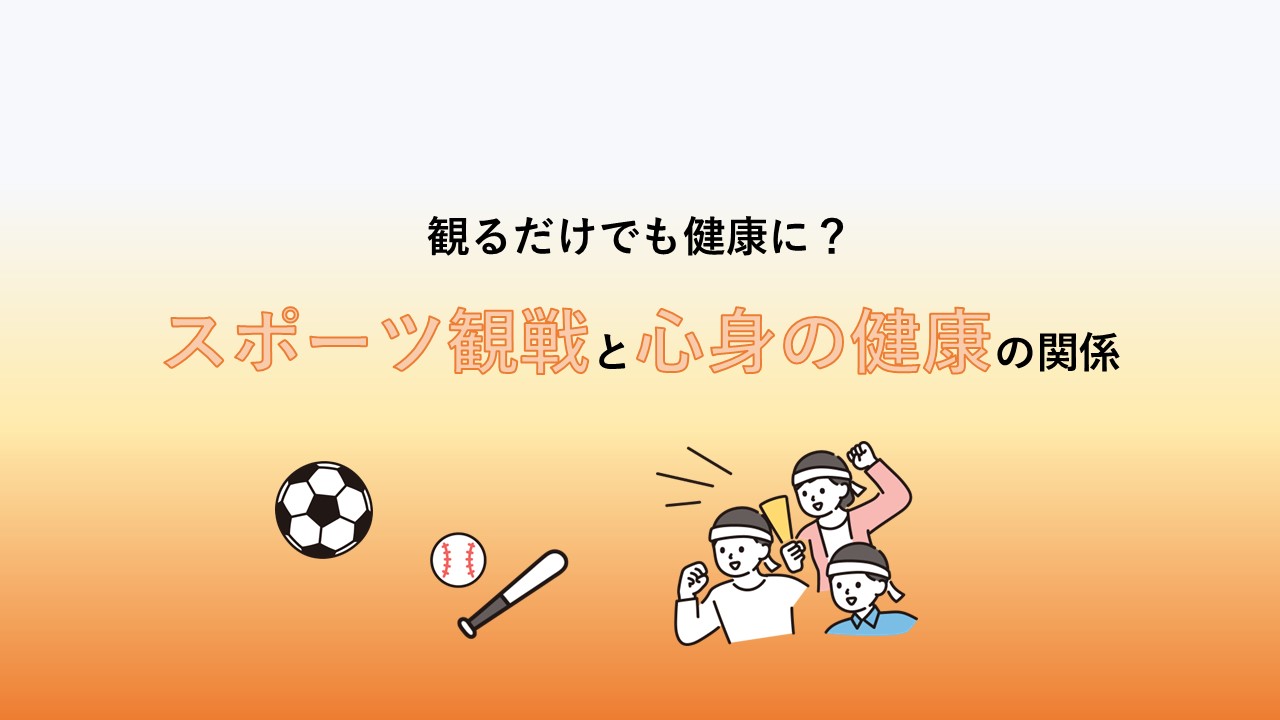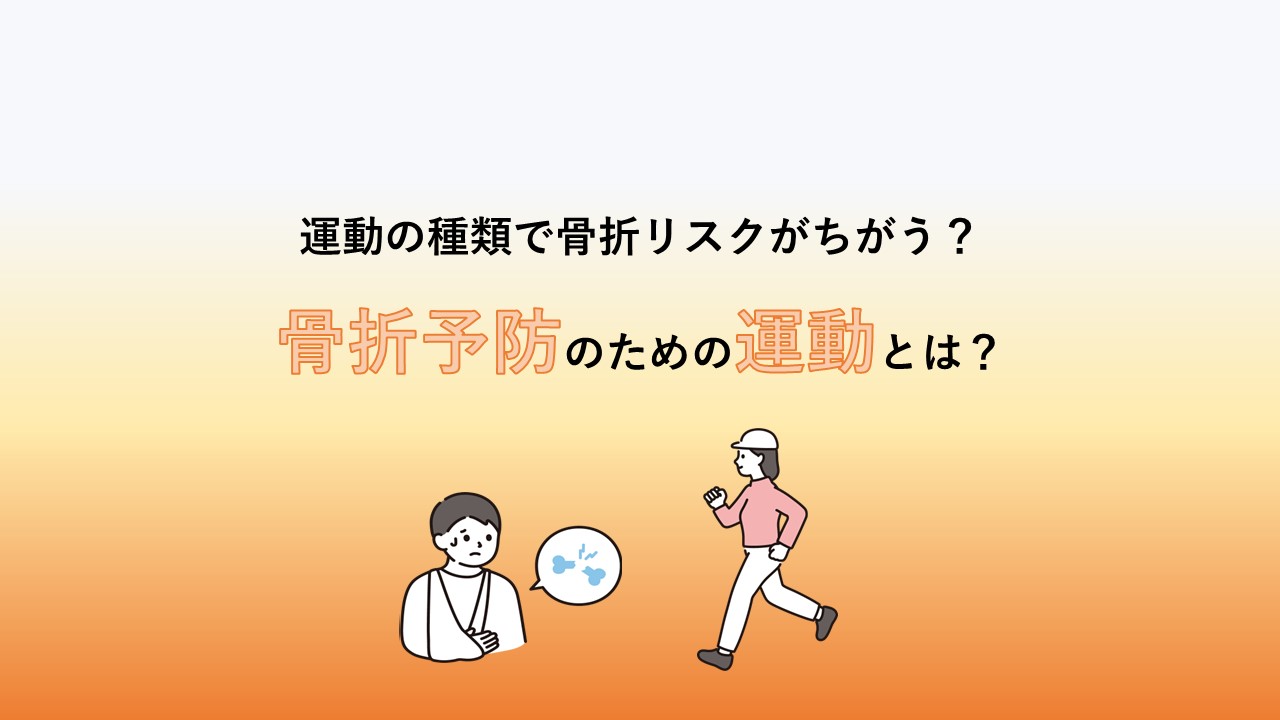- 運動
Born to run: 進化医学の視点から運動の重要性を考えましょう
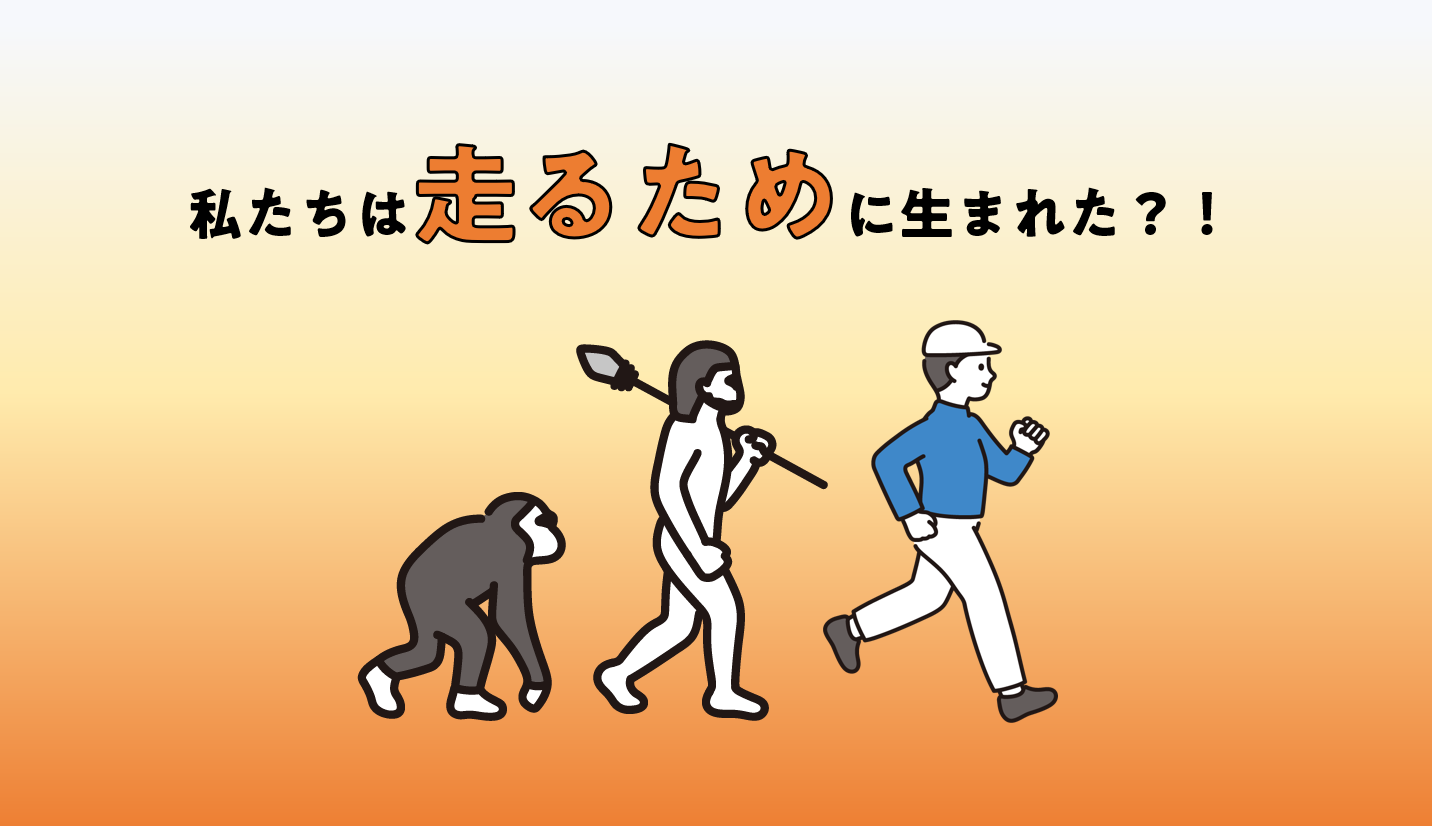
Nature(国際的な週刊科学ジャーナル)にチンパンジーとヒトの解剖学的特徴を考察し、ヒトは走るために生まれてきた(Born to run)ことが発表されました。
その論文を紹介すると共に運動や身体活動の重要性を説明したいと思います。
「進化医学」という言葉を聞いたことがありますか。1990年代頃から着目されたコンセプトで、「ダーウィン医学」とも呼ばれています。病気の原因の解明に進化学の視点を導入して、遠因にさかのぼって理解しようとするものです。進化医学は、直接治療に役立ったりすることはありませんが、病気の原因を理解し対策を考えるには重要な視点を提供してくれると考えられています。
例えば痛風は、血中の尿酸値が高くなることで発症する病気で、かつてはアレキサンダー大王やルイ14世などが罹患したことから「帝王の病」とも呼ばれています。実は、霊長類は、進化の過程で尿酸を分解する酵素を失っているのです。尿酸には酸化ストレスを抑える抗酸化能力があるため、進化医学ではこれは有利に働いたと考えられています。夜行性の哺乳類から進化した霊長類は、昼間、樹上生活することで強い紫外線に曝されるなど、厳しい自然環境の中で生存するために、尿酸を高め抗酸化能力を高めていた可能性が考えられています。しかし、現在はそれが高尿酸血症や痛風などの生活習慣病の遠因になっているのです。
それではここで、進化医学の視点で身体活動・運動を行うことの意義を捉えてみたいと思います。我々ホモ・サピエンス(Homo sapiens)は、約30万年前に出現したとされています。その後、1万2千年前から農耕牧畜が始まったと言われており、それまでは狩猟採集で生活をしていました。”30万”、”1万2千”という大きい数字からピンときていないかもしれませんが、30万年のうち1万2千年はわずか4%です。つまり、ホモ・サピエンス出現から、96%は狩猟採集をして過ごしていたことになります。
ヒトには、野生動物のような爪や牙もありません。筋力も野生動物と比べると弱そうです。ヒトと犬で走る速さを比較してみますと、世界最速の犬はグレートハウンドで、時速70km、100mを5秒37で走るそうです。一方、世界最速のヒトは、ウサイン・ボルト、100m 9秒58、これは時速37.58kmに相当します。また、柴犬でも時速35km、一般成人男性でも時速20km前後です。それでは、弓矢や槍などの道具のない時代、どうやってヒトは野生動物を狩猟していたのでしょう。
答えは、「持久狩猟」です。野生動物を走って追いかけ、バテて動けなくなったところで捕らえていたと考えられているのです。つまり、短距離では圧倒的に犬にもかなわないヒトですが、持久走には強いとされています。ヒトは毛皮で覆われていないので、汗をかいたり、体表面に血液の流れを増やすことで、効率的に体温を下げ、身体の中の温度(核心温といいます)を37度に保つことができます。しかし、毛皮でおおわれた野生動物はうまく体温調整をすることができません。そのため、長時間走り続けると体温が上昇し、ヒトよりも野生動物の方が先にバテてしまう、ということになります。このように、我々ホモ・サピエンスは、走ることが得意な動物であったがため、今の現在まで生きながらえてきたといえるでしょう。
ヒトとチンパンジーの解剖学的特徴を捉えた論文が2004年にBrambleとLiebermanによりNatureで発表され(Nature 2004)、大臀筋・項靭帯・土踏まず・アキレス腱が、チンパンジーと比べヒトの方が発達していることが示されました。これらの構造は、すべて走る際に必要なものです。
BrambleとLiebermanは、このように表現しています。
「Born to run」ヒトは走るために生まれた
ホモ・サピエンスの歴史の96%を、狩猟採集により走ることで生きながらえてきた我々の現在はいかがでしょうか。走ることに特化して進化した我々は、走らなくても食べることができるようになり、それにより生活習慣病を抱えることになった、ということも考えられます。
これまで、色々な視点から運動すること、身体活動を増やすことの意義を書いてきました。いまここで、30万年のホモ・サピエンスの歴史に思いを馳せ、その96%は狩猟採集民であったという事実を受け止めましょう。いきなり“走りましょう”でなくてもいいです。
まずは歩くことから、そして、スロージョギングをはじめることから、また、運動ではなく普段の生活での活動を少しでも身体を動かす方に意識することから、はじめてみませんか。
(参考図書・文献)
Bramble, D., Lieberman, D. Endurance running and the evolution of Homo. Nature 2004; 432: 345–352.
Lieberman, D., Venkadesan, M., Werbel, W. et al. Foot strike patterns and collision forces in habitually barefoot versus shod runners. Nature 2010; 463: 531–535.
以下は、読み物としても興味深いですので、是非読んでみてください。
・井村裕夫著.進化医学「人への進化が生んだ疾患」羊土社 2013
・ダニエル・E・リーバーマン著(塩原通緒訳)「人体600万年史 科学が明かす進化・健康・疾病」(上・下) 早川書房 2015
・ジャレド・ダイアモンド著(倉骨彰訳)「昨日までの世界」(上・下) 日本経済債新聞出版社 2017
・ランドルフ・M・ネシーら著(長谷川眞理子ら訳)「病気はなぜ、あるのか 進化医学による新しい理解」 新曜社 2001